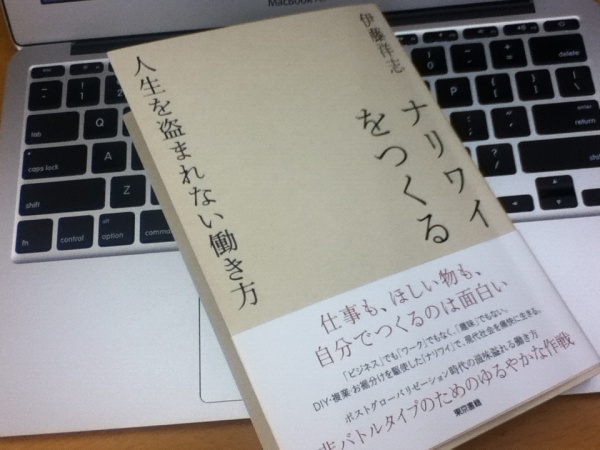どうも@takasugiuraです。
最近、書店に行くと「生き方」とか「働き方」の本が溢れていて、かつランキングでも上位を占めていることがままあります。
これは今、既存の働き方に疑問を持ち始めていて、新たな道を模索している人が増えてきている証拠なのかなと感じます。
丁度そういった働き方の転換点なんだと思います。私自身も新しい働き方を模索している身なので、肌で感じます。
そんな流れで目に留まったのがこの書籍。
「ナリワイ」とはどういうもので、どんな生き方なのか?これからは「ナリワイ」が最大のリスクヘッジになると著者は言います。では、いくつか気になったポイントを紹介したいと思います。
ナリワイの定義
「ナリワイ」とは恐竜ビジネスモデルから微生物ビジネスモデルへ転換を図ろうというものだ。
大きく賭けて勝負に出て、ハイリターンというビジネスでは無く、身の回りのできる事を小さな自営業と機能させ、独自の経済圏を作って暮らすということだと著者は言います。
切瑳琢磨して体育会系のノリで行う既存の起業スタイルではなく、近所の小さなニーズを拾い集めて、ゆるやかに暮らそうという提案です。
身の回りには小さなニーズは無数に存在します。そんなビジネスとしては成立しないレベルの小さなニーズを組み合わせて自分の「ナリワイ」を作っていく。
身の回りのモノ、仕事を自分の手で組み上げていく。
これからはそんな手作りの暮らしが真の安定と豊かな人生をもたらすんですかね。
そもそも仕事は自分でつくるもの
そもそも仕事の起源は、面倒な事をやる気のある人が担当することで生まれるものでした。誰かの役に立っていたり、楽しませていることができているから仕事になっているんですね。
人間、生きている以上何らかの価値を生みながら暮らしています。雇用されるか、自営でやるかは、その価値が企業で生み出すのか、個人で生み出すかの違いでしかありません。
個人の意思と責任で仕事をして試行錯誤することで、価値を創出する。それがナリワイとしての仕事。
専門性や特殊な才能は必ずしも必要な訳ではないと著者は言います。
プロ化してしまったものは、どうしても効率化され完璧を求められ、遊びの余裕が無く、面白みに欠けてしまうんですね。
完成度よりオモシロさを重視したほうが、全体として良いのではということです。
ナリワイのつくりかた
著者は「足下を見る」ことでナリワイを見つけることができると言っています。
日常生活の違和感を見つけ、それを起点に思考を深めていきアイデアを生み出すというもの。
「なぜ?」という問いかけより、「そもそも」という言葉を使って考える。「なぜ」では既存の枠組みから乗り越えることができないからという理由だそうです。
例えば、「なぜ車が売れないのか?」じゃなくて「そもそも、こんなに車を売る必要があるのか?」と思考する。
すると、違う次元での思考ができるというものです。
日常の中にネタは無数にころがっています。その現実の亀裂、ゆがみにどれだけ気づけるか、それがポイントということですね。
そして最初はうまくいかないことを知らないといけない、試行錯誤しているうちにウマくなるという前提を理解することが大事なんですね。
さいごに
アイデアをカタチにしてそれを実行に移す。
やりながら軌道を修正しながら、モノにしていく。
全て個人の責任で。それが「ナリワイ」というもの。
雇用が無いという前に身の回りで人の役に立つことをして暮らしましょうという提案です。
「仕事は自分でつくる」という熱いメッセージが詰まった1冊です。
自由で豊かな生き方の選択肢の一つとして今後定着してくかもしれません。
既に動き出している人は無数にいます。
この流れ、生き方はもっと加速していくのは間違いありません。
あなたの「ナリワイ」見つけてみませんか?
ではまた。